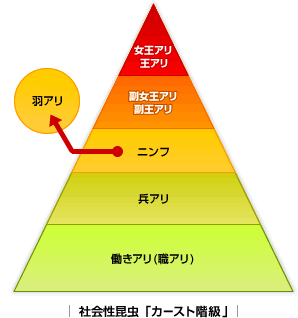Team Ants Militly Blog
蟻について
-
界:動物界 Animalia
門:節足動物門 Arthropoda
綱:昆虫綱 Insecta
目:ハチ目(膜翅目) Hymenoptera
亜目:ハチ亜目 Apocrita
上科:スズメバチ上科 Vespoidea
科:アリ科 Formicidae
-
アリは、ハチ目・スズメバチ上科・アリ科に属する昆虫である。体長は1 mm-3 cmほどの小型昆虫で、人家の近くにも多く、身近な昆虫のひとつに数えられる。原則として、産卵行動を行う少数の女王アリと育児や食料の調達などを行う多数の働きアリが大きな群れを作る社会性昆虫。 なお、シロアリは大きさや集団生活をすることなどがアリに似るが、アリとは全く別の仲間の昆虫である。
-
熱帯から冷帯まで、砂漠・草原・森林など陸上のあらゆる地域に分布する。多くは地中に巣を作って家族単位で生活するが、枯れ木や竹に巣を作るものや、卵・幼虫・蛹共々移動しながら生活する種類もいる。
一般認識としてハチとアリは区別されているが、多くが毒針を持たない事、生殖目的以外では翅を持たずに地面で生活する事から区別されたと考えられる。しかしながら、実際にはスズメバチやベッコウバチに近縁なグループで、アリ科の動物は全てハチそのものである。スズメバチから見ても、同じハチとして認識されているミツバチよりもアリ類の方が近縁である。
体色は黒いものが多いが、黄色、褐色、赤色などの種類もいる。翅はないが、繁殖行動を行う雄アリと雌アリには翅がある。なお、腹部の前方の節が細くくびれて柄のようになった「腹柄節」は、昆虫でもアリだけにある器官であり、狭い穴の中での生活に適応すべく役割を果たしている。
大顎が発達し、餌をくわえたり外敵に噛みついたりできる。さらに腹部先端にはハチと同じように毒腺を持ち、針で刺すことのできるものも少なくない。



日本産の主な種類
日本では10亜科280種以上が知られている。日本のアリ相は熱帯性と冷寒帯性の境目のようなものだが、これは1万年前、最終氷期後に成立した。
-
ヤマアリ亜科
-
クロオオアリ - 全国に生息。働きアリの体長は12mmにもなる。開けた場所の地中に営巣し、5-6月に結婚飛行を行う。
-
ムネアカオオアリ - クロオオアリに似ているが、胸部と腹柄節にかけて赤褐色をしている。朽ちた木に営巣し、5-6月に結婚飛行を行う。
-
ミカドオオアリ - 体長8-11mm。朽ちた竹に営巣するアリで、コロニー規模が大きくなってくると巣別れする。
-
トゲアリ - 体長は8 mmほど。背部に、6本のトゲを持つ。一時寄生をする種で、クロオオアリ・ミカドオオアリ・ムネアカオオアリなどの大型種に寄生する。この寄生の際、トゲアリの女王は単独で相手のコロニー内に進入し、その女王を組み敷いて殺すのだが、トゲアリの女王はその時相手の体から体液を吸っていることが認められている。
-
アカヤマアリ - 体長6-8mm。奴隷狩りという行動を取ることで知られる。クロヤマアリなどの幼虫などをさらってきて混生する。
-
クロヤマアリ - 草原など日当たりの良い土の露出したところに、深さ1mほどになる巣を作る。主にアリマキの出す甘露や花の蜜、昆虫の死骸などを食べるが、花びらや土筆の穂を食べる姿も見られている。関東型と関西型に大別され、関東型は一つの巣に一匹の女王が居るが、関西型は複数の女王が同じ巣で暮らしている。
-
サムライアリ - クロヤマアリの巣を襲って幼虫やさなぎをさらい、奴隷として働かせる習性がある。これを奴隷狩りという。
-
トビイロケアリ
-
-
フタフシアリ亜科
-
クロナガアリ - 草原に生息。地下4mにも達する細長い巣を作る。秋に地上に現れ、イネ科植物の実を採集して主食にする。
-
アシナガアリ - 全国に生息。主に東日本では平地、西日本では平地から山地までの林縁、林内の土中や石下に営巣する。腹曲げ行動を行わない。日本全国に15種類ほどが知られる。
-
イエヒメアリ - 体長2-3mm。体色は頭部と胸部が淡黄褐色から褐色。屋内に巣を作り大量発生することがあり、防除が難しい害虫として問題になる。(実際に屋内で甘いものをこぼすとイエヒメアリが集ることもある)
-
オオズアリ - 働きアリは体長2.5mmほどだが、一部は体長5mmほどの兵隊アリとなる。兵隊アリは頭が大きいのでこの和名がある。日本では西日本に多く、東日本には近縁のアズマオオズアリが多い。
-
キイロシリアゲアリ - 腹部が上向きに吊り上るのでこの和名がある。小型で琥珀色をしている。
-
ハリブトシリアゲアリ - 獲物や外敵を攻撃する際に腹部を頭上までそりかえらせて毒針の先端から刺激臭のある毒液(蟻酸ではない)を出す。テラニシシリアゲアリに対して褐色がかっていて、一回り大きい。後胸部の前伸腹節刺が太く短い。
-
テラニシシリアゲアリ - 獲物や外敵を攻撃する際に腹部を頭上までそりかえらせて毒針の先端から刺激臭のある毒液(蟻酸ではない)を出す。黒く、ハリブトシリアゲアリよりも一回り小さい。後胸部の前伸腹節刺が細く鋭い。
-
クシケアリ
-
アミメアリ - 体長2.5mm。頭部、胸部に網目状の模様がある。雌アリを持たず、働きアリが産卵してコロニーを維持する。雄アリはまれにみられる。巣穴は作らず、石の隙間や倒木に集団を形成し、頻繁に移住する。大きなコロニーでは数十万匹にも達する。殺虫剤に抵抗性を持つコロニーがある。
-
ムネボソアリ
-
トビイロシワアリ - 体長2.5mm。頭部、胸部に縦にしわ状の模様がある。平地の石下などに営巣する。ほぼ日本全国に分布する。西日本で最も普通に見られるアリ。
-
アメイロアリ - 腹部が水飴のような透明な褐色をしている。蟻の中では小型。
-
コツノアリ
-
-
カタアリ亜科
-
ルリアリ
-
-
ハリアリ亜科
-
オオハリアリ - 湿気のある場所に多い。腹部先端に発達した毒針を持ち、刺される事故がよく発生する。
-
トゲズネハリアリ
-
ニセハリアリ
-